ゴルフ場経営における収益性改善は、いつの時代も経営者の頭を悩ませる重要な課題です。従来の集客方法やコスト削減策が限界を迎えつつある今、新たな成長エンジンとして注目されるのが「地域社会・メンバーとの共創」です。
単なる連携を超え、共に新しい価値を創り出すこの取り組みは、いかにしてゴルフ場の収益向上に結びつくのでしょうか?
本稿では、国内外の先進事例を紐解きながら、その可能性と具体的な戦略を探ります。
「共創」がゴルフ場経営にもたらす収益向上のメカニズム
現代のゴルフ場経営において、「共創」とはゴルフ場が地域社会、メンバー、NPO、地元企業といった多様なステークホルダーと能動的に関わり、共通の目標達成や課題解決に向けて、それぞれの持つリソースやアイデアを出し合い、新しい価値やサービスを共に創り上げていくプロセスを指します。このプロセス自体が、ゴルフ場に多大な経済的恩恵をもたらす可能性を秘めています。
「より良いゴルフ場運営」をステークホルダー全員で目指す中で、環境保全、高品質なコース、顧客満足度の向上、そして健全な財務基盤が自然と構築されます。これは、共創によるエンゲージメントの高まりが、利用頻度の増加、顧客単価の上昇、口コミによる新規顧客の獲得、さらには運営効率の改善に直結するためです。
一般社団法人格(GIA)ゴルフ場と株主会員制ゴルフ場は、それぞれ異なる背景と構造を持ちながらも、「共創」を通じて経営改善と収益向上を目指しやすい特性を持っていると言えるでしょう。
国内外の先進事例に学ぶ:「共創」が生み出す収益改善の具体像
1. 日本国内における「共創」モデルとその収益インパクト
「参加型コース管理」によるコスト削減と利用促進の共創
ブリックアンドウッドクラブ(千葉県市原市)では、メンバーに担当ホールを割り当てることで、そのホールにオーナーシップを持ってもらい、目土などを中心とした保全活動を推進しています。また、東京国際ゴルフ倶楽部(東京都町田市)では、NPOボランティア(主にメンバーや地域住民)が目土作業に主体的に参加し、その貢献に対してポイント(施設利用券など)が付与されます。
ボランティアとの共創によるコースメンテナンスは、直接的な人件費削減に繋がります。さらに、参加者はコースへの愛着を深め、クラブへのロイヤリティが向上し、自らの利用頻度を高めるだけでなく、知人への推奨など口コミによる集客効果も期待できます。ポイントシステムは、施設内消費を促し、客単価アップにも貢献し得ます。
「真向法体操」による地域コミュニティとの健康共創
国の定める9月の「健康増進普及⽉間」の期間中に、日本ゴルフ協会(JGA)がゴルフを通じた健康維持増進を目的に「ゴルフ健康週間」を設定しました。「ゴルフ健康週間」では、ゴルフを通じた地域住⺠の健康維持増進のため、全国で「JGA WAG スクール1Day プログラム(1⽇体験版)」など健康に関する数々のイベントが実施されています。
また、東京国際ゴルフ倶楽部(東京都町田市)が施設の一部を開放し、地域住民(特にシニア層)の健康増進というニーズに応える形で公益社団法人 真向法協会と連携し、体操教室を共催・運営しています。参加者の増加に伴い開催頻度を増やすなど、ニーズに合わせた柔軟な対応が特徴です。
地域住民との新たな接点を共創することで、ゴルフ未経験者層へのリーチが可能となり、新規顧客開拓の機会が生まれます。また、既存シニアゴルファーの健康寿命延伸は、ゴルフライフの長期化を促し、安定的な施設利用に繋がります。ゴルフ場が地域の健康拠点としての役割を担うことで、ブランドイメージが向上し、地域からの信頼獲得は、様々な面でポジティブな経済効果(例:イベント開催時の集客、風評リスクの低減など)をもたらします。
「地域まるごと活性化」を共創する多角的連携
セブンハンドレッドクラブ(栃木県さくら市)は、さくら市と「フットゴルフの聖地化」を共同推進しています。また、地域団体と夏祭りや市民体育祭を共同開催しています。自社で生産するいちごを使用したり、農産物直売所「菜っ葉館」の指定管理を受けることで、地元生産者と「食の魅力」を共同開発・提供しています。
フットゴルフ導入は、ゴルフ以外の利用者層を呼び込み、施設の時間帯別稼働率を向上させ、新たな収益の柱を確立します。地域イベントは、施設の露出度を高め、潜在顧客へのアプローチとなると同時に、飲食部門の売上増にも直結します。地元食材の積極活用は、レストランのメニューの独自性と質を高め、集客力と客単価の向上に貢献します。これらの「地域との価値共創」が、直接的・間接的にゴルフ場の収益基盤を強化します。
このようなゴルフ場の事例に加え、公益社団法人 ゴルフ緑化促進会はゴルフ場が持つ自然環境を資源と捉え、地域住民やNPO、学校と連携し、環境保全活動や環境教育プログラムを共同実施しています。
環境保全への取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たすことでブランドイメージを向上させ、環境意識の高いゴルファー層に強く訴求します。これにより新規顧客獲得やロイヤルティ向上が期待できます。また、間伐材の有効活用や自家製堆肥の利用は、廃棄コストや購入コストの削減に直結します。環境教育の場としての提供は、将来のゴルファー育成という長期的な視点での投資となり、地域社会との良好な関係は、安定経営の基盤となります。
2. 北米:生物多様性、包括性、ボランティアリズムの育成
「インクルーシブな地域ハブ」としての価値共創
Corica Park Golf Course(アメリカカリフォルニア州)は多数のNPOや地域団体とパートナーシップを結び、ゴルフコースを多様な地域活動のプラットフォームとして提供しています。ジュニアプログラム、健康増進プログラム、地域イベントなどを共同企画・運営しています。
公平性、環境意識、コミュニティスペースとしての機能に重点を置く市営コースで、有色人種やゴルフ未経験者の参加率が高い無料の青少年プログラムを実施し、「ゴルフライフスキル」(積極性、忍耐、決断力など)の育成にも力を入れています。また、30以上の団体と提携し、NPO向け無料会議スペースの提供、ヨガやアートセラピーのための緑地開放、小規模ビジネスフェアの開催など、ゴルフ以外の目的での利用も促進しています。環境面では、再生水の利用、耐乾性芝生の導入、堆肥化教育、送粉者用庭園の設置、生分解性のクルミ殻カート道などを採用しています。

多様なプログラム提供により、従来ゴルフとは無縁だった層をゴルフ場に呼び込み、新たな収益機会を創出します。特に無料や低価格のジュニアプログラムは、将来の優良顧客育成に繋がり、長期的な収益基盤を強化します。施設の多目的利用は、時間帯別・曜日別の稼働率を平準化し、収益の安定化に貢献します。環境配慮型運営は、企業からのイベント誘致やスポンサーシップ獲得においても有利に働く可能性があります。
「バードフレンドリー・ゴルフコース」:「自然保護」と「体験価値」の共創
アメリカのゴルフコースでは、環境団体や地域ボランティアと連携し、野鳥の生息環境保全活動を共同で実施しています。教育プログラムや情報発信も行っています。
環境保全への積極的な姿勢は、ゴルフ場のブランドイメージを高め、特定の趣味を持つ層(バードウォッチャーなど)への訴求力を強化します。ガイド付きの自然観察ツアーなどを企画すれば、ゴルフ以外の新たな収益源となる可能性もあります。ボランティアの活用は、一部の管理コストを軽減する効果も期待できます。
「Adopt-a-Hole(ホール里親制度)」:「コース愛」を育むメンバーとの共創
アメリカでも、日本のブリックアンドウッドクラブと同様に、メンバーが特定のホールを担当し、自主的にディボット修復などの軽微なメンテナンスを行うボランティア制度です。West Brook Golf Club(アメリカ)では年間2000時間以上のボランティア活動が行われていると報告されています。
メンバー自身がコース管理の一部を担うことで、コースへの愛着と責任感が醸成されます。これは、メンバーシップの満足度向上、継続率の向上、さらには新規会員への口コミ効果として現れ、安定した収益基盤の維持に貢献します。また、グリーンキーパーの負担を軽減し、専門業務への集中とコース全体の品質向上を可能にします。
3. ヨーロッパ:持続可能な運営と組織的ボランティア活動の先進性
欧州のゴルフ場における多様な「サステナビリティ共創」
Golf Club de Naxhelet(ベルギー)では、GEO認証を取得し、地元業者からの調達や有機的なメンテナンスを重視しています 。具体的には、環境配慮型製品や有機肥料の使用、雨水利用の灌漑システム、高性能気象観測装置による精密な水管理、電動カートの導入などです。イベント時には地元産の旬の食材を提供することも徹底しています。

Real Club Valderrama(スペイン)では、ヨーロッパで初めてオーデュボン国際環境優秀認証を取得した先駆者であり、先進的な灌漑システムによる19%の節水、雨水貯留池の建設、非プレーエリアでの灌漑停止とマルチング材(コルク樫の樹皮)利用、野生生物の専門家によるモニタリングと生息地保護、機械のGPS追跡によるルート最適化と燃料削減、そして化学製品の段階的削減から完全撤廃を実現しています。
地産地消は、食材コストの最適化と輸送コスト削減に繋がるだけでなく、レストランのメニューに独自性を与え、顧客満足度と客単価の向上に貢献します。高度な環境管理は、水・光熱費・薬剤費などの運営コストを大幅に削減します。地域住民を巻き込んだイベントは、集客と施設利用の促進に繋がります。
イギリスでは、イングランドゴルフ協会や英国・国際ゴルフグリーンキーパー協会(BIGGA) が、ボランティアの募集、管理、研修、表彰に関する体系的な支援を提供しています。イングランドゴルフは、職務記述書のテンプレート提供、広報アドバイス、新規プレーヤーをサポートするボランティア向け研修、感謝状や表彰制度といった具体的なリソースを提供しています。これらの公式な組織や専門機関による支援は、ボランティア活動や環境プログラムの効果と持続性を大幅に高める上で重要な役割を果たしています。草の根の熱意は不可欠ですが、構造化されたサポートが、これらの取り組みを拡大し、標準化し、維持するのに役立っています。
4. オセアニアおよびその他地域:ウェルネス、青少年育成、フィランソロピーにおける革新
「健康と就労支援」を通じた社会価値共創
Wellness Warriors Golf Squad(オーストラリア)は、ゴルフとライフコーチングを組み合わせ、レジリエンス(精神的回復力)、規律、自信の育成を目指すプログラムです 。プロショップ業務、飲食サービス、グリーンキーピングといったゴルフ場での実務経験、ライフスキル開発、PGAプロによる指導などが含まれ、NDIS(国民障害保険制度)による資金提供オプションも用意されています。
イギリスのゴルフ財団(R&A支援)によるUnleash Your Drive in Schoolsは、ゴルフを通じて子供たちの精神的ウェルビーイング向上を目指す学校向けイニシアチブです 。特別仕様の用具を使用し、集中力、呼吸法、ポジティブな自己対話といったメンタルタフネスツールに焦点を当てています。これらのプログラムは、ゴルフを個人の成長とコミュニティ開発のためのツールとして位置づけ、その価値提案をスポーツやレクリエーションの領域をはるかに超えて拡大しています。
国際的なトレンドとして、ゴルフコースの再野生化(リワイルディング)も注目されています 。スコットランドのカイルのプロックやカリフォルニアのサンジェロニモ、日本の春日井カントリークラブの改修のように、かつてのゴルフコースやその一部を自然生息地に戻す動きです。これは、過剰な水利用や生息地破壊といった懸念に対応するものです。パーマカルチャー(持続可能な農業をもとに、人と自然が共に豊かになるような関係を築いていくためのデザイン手法)の概念をゴルフコースに応用し、自生植物の導入、コミュニティガーデンの設置、ウェルネスプログラムの統合を通じて、生態系とコミュニティハブとしての再生を目指す提案もなされています 。
アメリカのCongaree Global Golf Initiativeは、フィランソロピー(慈善活動)を重視したゴルフクラブのモデルで、恵まれない若者への機会提供と地域社会への貢献を目的としています 。また、PGA of Americaは、小規模・地元・多様な背景を持つ事業主との連携を奨励する包括的な調達イニシアチブを推進し、サプライヤーポータルの活用や商工会議所との連携を通じて、地域経済の活性化とゴルフ文化の多様化を目指しています 。
これらの多様な事例から、「共有価値」という概念が強く浮かび上がってきます。つまり、ゴルフコース(運営面、財務面、評判面)とコミュニティ・環境の双方に同時に利益をもたらすように設計された取り組みが主流になりつつあるのです。これは、純粋な慈善活動でも純粋な商業的アプローチでもない、双方の利益の一致がプログラムの長期的な持続可能性の鍵となる考え方です。
「共創」をゴルフ場の収益に繋げるためのキーファクター
これらの「共創」を成功させ、持続的な収益向上という果実を得るためには、以下の要素が不可欠となります。
- 明確なビジョンと経営者のコミットメント:経営者が「共創」の戦略的価値を理解し、全社的な取り組みとして推進する強い意志が求められます。このビジョンが、地域社会やメンバーの共感を呼び、積極的な参加を促します。
- 「三方良し」の価値提案:ゴルフ場、パートナー(地域社会・メンバー)、そして顧客(利用者)の全てに具体的なメリットがある「Win-Win-Win」の関係を設計することが、共創を持続させる上で最も重要です。これにより、各ステークホルダーの自発的な貢献が促され、結果として新たな価値が生まれ、収益に繋がります。
- オープンなコミュニケーションと対話:共創のプロセスでは、多様な意見やアイデアが交錯します。これらを積極的に引き出し、建設的な対話を通じて磨き上げるためのオープンなコミュニケーションチャネルの確保が、革新的なサービスや収益機会の発見に繋がります。
- 多様な参加インセンティブと成果の共有:ボランティア活動やアイデア提供に対し、金銭的報酬だけでなく、施設利用優待、表彰、活動成果の共有といった多様なインセンティブを用意することで、参加者のモチベーションを高め、継続的な関与を促します。満足した参加者は、ゴルフ場の良き理解者・推奨者となり、長期的な収益に貢献します。
- 地域特性の尊重と独自性の追求:自社のゴルフ場が置かれた地域ならではの文化、歴史、自然、人材といった資源を最大限に活かし、他にはない独自の「共創」モデルを追求することが、競争優位性を確立し、収益機会を最大化します。
- 「共創ストーリー」の積極的発信:共創によって生まれた成功事例や感動的なエピソードを、「物語」として内外に発信することで、ゴルフ場のブランドイメージが感情的なレベルで向上し、ファンを増やし、新規顧客の獲得やメディア露出による広告効果も期待できます。
- 柔軟な試行錯誤と継続的改善:最初から完璧な「共創」モデルを求めるのではなく、スモールスタートで試行錯誤を重ね、関係者からのフィードバックを真摯に受け止め、柔軟にプログラムを改善していく姿勢が、変化する市場ニーズに対応し、収益機会を逃さないために重要です。
- 課題解決プロセスも「共創」で:連携には困難が伴うこともありますが、その解決プロセス自体を関係者との「共創」の機会と捉え、共に知恵を絞ることで、より強固な信頼関係と、予期せぬ新しい解決策(=新たな価値)が生まれることがあります。
未来への展望:「共創」こそが、ゴルフ場収益の未来を照らす
ゴルフ場が地域社会やメンバーと真摯に向き合い、彼らの持つ知恵や情熱、リソースを借りながら、共に汗を流し、新しい価値を「共創」していく取り組みは、もはや単なる理想論ではありません。それは、ゴルフ場のブランド価値を高め、新たな顧客を惹きつけ、運営効率を最適化し、そして何よりも持続的な収益成長を実現するための、極めて実践的かつ効果的な経営戦略です。
本稿でご紹介しました国内外の事例は、それぞれの地域特性や課題に応じて多様な「共創」の形があることを示しています。これらのヒントを元に、各ゴルフ場ならではの「共創」の物語を紡ぎ出し、地域に愛され、選ばれ、そして経済的にもしっかりと潤う、次世代のゴルフ場経営を実現されることを期待いたします。
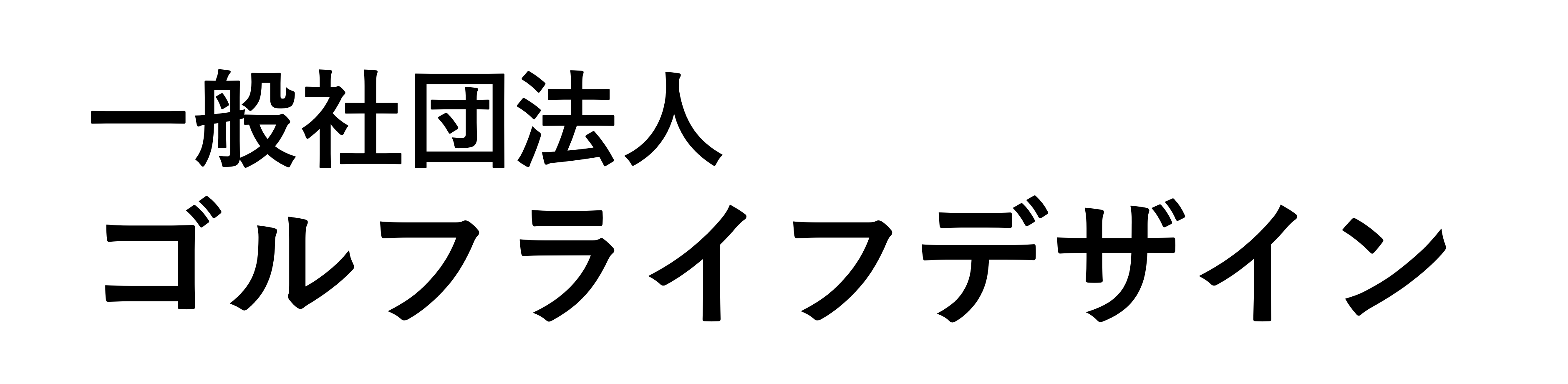

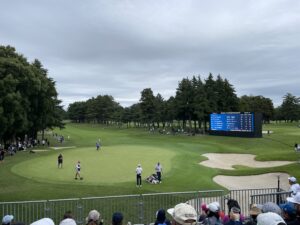






コメント