住地ゴルフCOO/ゴルフライフデザイン代表理事の木下です。
愛知県春日井市にある春日井カントリークラブが、開場60周年を機に、井上誠一の設計思想と最先端技術が交差させる東コースのコース改修を実施しました。老朽化、人手不足、温暖化という現代の課題に立ち向かう、未来への挑戦の全貌をレポートします。
1964年(昭和39年)の開場以来、中部地区の名門としてその歴史を刻んできた春日井カントリークラブ。戦後の日本ゴルフ場設計の巨匠、井上誠一氏が手がけたこの地が、開場60周年という節目に大きな変革を遂げました。
「戦略性」「美観」「持続可能性」を掲げ、米国のゴルフプラン社、デビッド・デール氏の手によって全面改修された東コース。先日行われたメディアツアー説明会では、伝統あるコースが現代の課題を克服し、未来へと踏み出すための「挑戦」に満ちた姿が明らかにされました。
秋晴れのコースで感じた「進化」と「戦略性」
説明会に先立ち、筆者も実際に改修された東コースをラウンドしました。
秋晴れの空の下、美しく色づき始めた紅葉の中でのプレーは格別でした。何より印象的だったのは、景観を損ねるヤード杭などが一切なく、洗練された美しい眺望が保たれていたことです。
以前、改修後まもない頃にもプレーする機会がありましたが、その時と比較して芝付きが格段に良くなっており、コースコンディションが向上していることを肌で感じました。
当日のグリーンは10.5フィート。近年、酷暑が続いていますが、それを感じさせない完璧な仕上がりで、ボールの転がりも素直で非常に気持ちよくパッティングを楽しむことができました。
プロジェクトマネージャーの大矢隆司氏は「コースとしての仕上がりはまだ時間がかかる」と謙遜されていましたが、既に素晴らしいクオリティに達していると感じます。
トークセッションで語られた通り、バンカーやコレクションエリアの配置は絶妙で戦略性が高く、まさに「何度回っても楽しめる」コース。「ぜひメンバーになりたい」と強く思わされる、挑戦意欲を掻き立てられるラウンドでした。


60年目の老朽化という現実に直面し、「清水の舞台から飛び降りる」決断
説明会の冒頭、代表取締役の松岡敏和氏は、改修に至った背景を率直に語りました。
「61年目を迎え、人間でいえば還暦。しかし、コースは様々な部分で悲鳴を上げていました。」
クラブやボールの飛躍的な進化は、井上誠一氏が意図したバンカーの位置を「おかしいではないか」と感じさせるものに変えました。バンカーは崩れ、排水は悪化。グリーンのサッチは蓄積し、何よりコースの“血管”であるべき散水の本管が「コレステロールが溜まった」状態となり、末端まで水圧が届かないという致命的な問題を抱えていました。
「毎年、億単位の補修費をかけ続けても、それは対症療法にしかならない。建物の改修と同じで、目に見えない配管や空調こそが重要です。どうせ投資するなら、中途半分な補修ではなく、次世代に『負の財産』を残さないよう、一気呵成にやるべきだ。」
松岡社長は、この一大プロジェクトを「清水の舞台から飛び降りる」覚悟であったと振り返ります。そのコンセプトは、「井上誠一先生が今、存命ならどういうコースを作るか」という伝統への敬意と、海外の最新ゴルフ場設計・コース管理部門の知見を融合させること。中部地区では前例のない、未来への大胆な先行投資でした。


国内初の最新技術が集結し、課題を希望に変える「持続可能性」
続いて登壇した松岡茂将取締役は、このプロジェクトが「挑戦」であったと強調します。彼が2020年に経営に参加して直面したのは、日本全国のゴルフ場が抱える共通の悩み、「老朽化」「人手不足」「温暖化」という三つの大きな課題でした。
「これらを解決し、『戦略性と美観、そして持続可能性を備えた21世紀のゴルフ場』を目指す。これが我々の挑戦でした。」
その「持続可能性」を実現するために導入された技術の多くは、国内初、あるいは最先端のものです。
- 散水システム(老朽化・人手不足対策): 従来のブロック単位の散水ではなく、海外ではスタンダードとなっている「スプリンクラー個別制御システム」を国内で初めて導入しました。ピンポイントで必要な量の水だけを散布でき、大幅な節水と管理の省人化を実現しています。
- バンカー(温暖化・人手不足対策): ゲリラ豪雨による水たまりや流水跡は、コース管理の大きな負担でした。高い透水性を誇る「ベタービリーバンカー」を採用することで、雨が降っても水が溜まらず、水抜き作業の人手を大幅に削減しました。結果、他の作業にリソースを集中できるようになったのです。
- 芝種(温暖化対策): 高温多湿の日本の夏に対応するため、最新の第7世代ベントグラス「オークリー」を採用しました。この夏も素晴らしいコンディションを維持し、その強さを証明しています。
- 無人芝刈り機とカート乗り入れ(人手不足対策): フェアウェイの無人芝刈り機を導入し、省人化を推進。さらに、深刻なキャディ不足に対応するため、2人乗りカートのフェアウェイ乗り入れを前提とした幅2.8mのカートパスを整備しました。誰もが快適にプレーできる環境を整えています。
驚くべきは、これだけの「管理のしやすさ」「プレーのしやすさ」を追求しながら、コースの戦略性は一切妥協されていない点です。改修後のコースレーティングは75.4、スロープレートは149という国内屈指の難易度を誇っています。
この挑戦と成果が評価され、春日井カントリークラブ東コースは、2026年に開催されるアジア競技大会(アジアンゲームス)の会場にも選定されています。


設計家とプロが語る「何度でも挑戦したくなる」戦略性の妙
説明会の後半は、設計を担当したデビッド・デール氏と、中部プロゴルフ協会会長でありコースセッターも務める桑原克典プロによるトークセッションが行われました。
桑原プロは、改修中の造形を見た瞬間に「ここでトーナメントをやってほしい」と直感したといいます。
「ここのバンカーは、ミスした人が入るネガティブな存在ではなく、攻略のための『ターゲット』になっている。さらにワングリーンとはいえ、グリーン上に2つも3つも面がある。上級者ほどピンポイントでその面に乗せなければならず、ゴルフ本来のターゲットスポーツとしての楽しさが詰まっている。」と絶賛しました。
デビッド・デール氏は、井上氏の優れたレイアウトを活かしつつ、球の転がりや角度を緻密に計算したと語りました。特にこだわったのが、グリーン周りに設けられた「コレクションエリア」と呼ばれる、くぼんだフェアウェイです。
「バンカーやラフではなく、あえて短く刈り込んだエリアにボールが集まるように設計しました。そこからはウェッジだけでなく、パターや他のクラブも選択できる。プレーヤーの技術と想像力が試され、何度プレーしても飽きないはずです」(デール氏)


コースセッターが抱える悩みを完全解消した「トーナメント運営の夢の舞台」
セッションはさらに熱を帯び、話題はトーナメント開催の適合性へと移りました。コースセッターとして中日クラウンズや日本プロのセッティングも担当した桑原プロは、既存コースが抱える「悩み」を吐露しました。
「多くのコースでは、傾斜が厳しくてピンを切れる面が少ない。結果、グリーンのポテンシャルは高いのに『スピードを落としてくれ』とお願いする本末転倒な事態すら起きています。しかし、春日井は『10日間連続で試合ができる』ほど面が豊富。キーパーに『どれだけでも硬く、速くしてください』とお願いできる。選手の能力を最大限に引き出すセッティングが可能です。」
さらに、トーナメント運営を悩ませるのが、雨による中断と進行遅延です。
「雨が止んでも、バンカーの流水跡の修復や水抜きに1時間半もかかり、日没サスペンデッドになることがあります。しかし、ここのベタービリーバンカーは、この1年、一度も流水跡も水たまりも発生しなかったと聞きました。これは、トーナメント運営側からすれば、まさに夢のような舞台です。」
デビッド・デール氏も、「難しさとは距離だけではない。グリーンの『硬さ(Firmness)』こそがプロを苦しめる最大の要素。このコースは、それを実現できる」と応じ、世界基準のセッティングが可能であることを示唆しました。


日本ゴルフ界の新たなベンチマークへ
総工費は約18億円。しかし、これは単なる修繕費ではありません。松岡社長が語ったように、「旧態依然のまま毎年補修費をかけ続ける」道を選ばず、「未来へ一気に投資する」という経営判断です。
デビッド・デール氏は、このプロジェクトを「環境的に持続可能なゴルフデザインと運営において、日本の新たなベンチマークを創造した」と総括しました。
桑原プロも「ここが日本のゴルフ界の指標になってほしい。次の世代へゴルフを引き継ぐ素晴らしいきっかけになる」と期待を込めました。
伝統の重みを受け止めつつ、勇気ある「挑戦」を選んだ春日井カントリークラブ。その決断が、日本のゴルフ場の未来を明るく照らす試金石となることは間違いないでしょう。
-1024x768.jpeg)
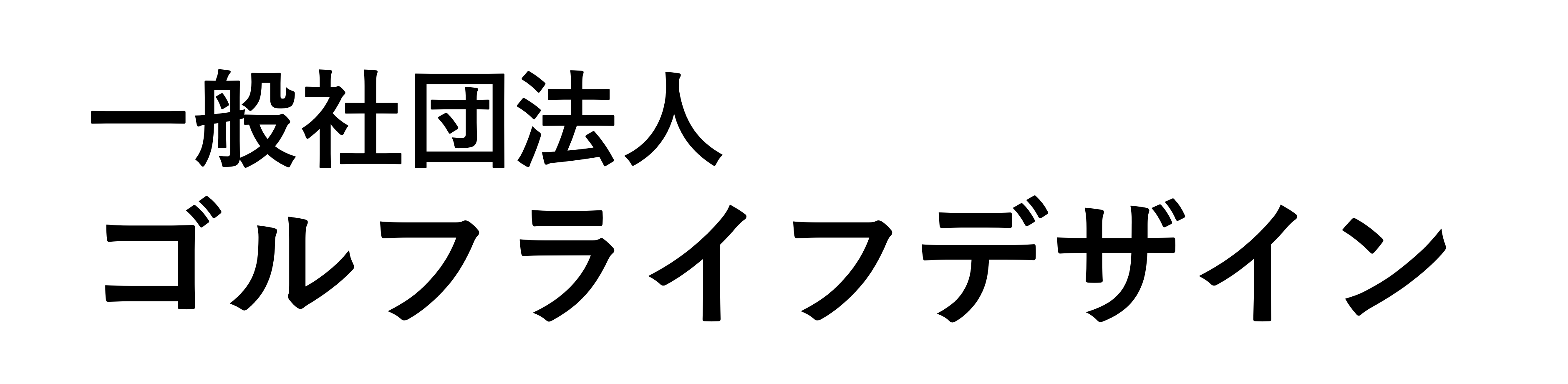
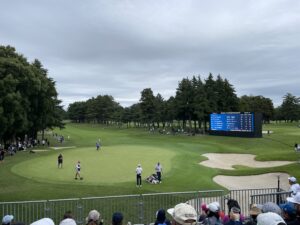







コメント